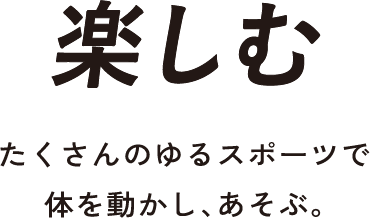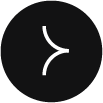「ナレッジでつなぐ、未来をつくる」をパーパスに掲げ、三井物産グループのデジタルソリューションプロバイダーとして、付加価値の高いICTトータルサービスを提供している「三井情報株式会社」様。コミュニケーションを目的とした新入社員研修や、ゆるスポーツ開発ワークショップにて、ゆるスポーツを活用いただいています。三井情報株式会社 取締役 蒲原 務様、実際にワークショップに参加した大鹽(おおしお)様に、当協会を選んでいただいた理由や、依頼して良かった点、参加された感想などをお話しいただきました。
「実践から学ぶ」社員の創造力を刺激する行動主導のアプローチ
ー ゆるスポーツ開発ワークショップを研修として取り入れた経緯を教えてください。
▼ゆるスポーツ開発ワークショップの詳細
開発テーマ:「クリケット」×「三井情報」
参加人数:14名
実施期間:2024年8月〜10月(全4回)
実施方法:2グループに編成し2種類のゆるスポーツを開発、開発した競技は社内でお披露目し体験会を実施
(蒲原さん)企業の研修では、デザイン思考やシステム思考などのフレームワークを学ぶことが多いですが、実際に業務で活用するのは難しいと感じていました。ゼロから新しいものを生み出す際、理論や思考方法を学んでも実践しないと身につかないからです。実践を通じて学ぶ機会を作ることが重要だと考えていたときに、新入社員向けのコミュニケーション施策の一環としてゆるスポーツ研修を導入した際、体験だけでなくスポーツ自体を考案するプロセスがあることを知りました。従来の、思考から実践へではなく、行動から始めるというアプローチが面白いと感じ、それが社員の創造力や発想力を伸ばすのに適しているのではないかと思い、今回のワークショップをトライアル実施することになりました。

ー 「クリケット」×「三井情報」をテーマにゆるスポーツを開発しました。貴社とクリケットとの関わりや取り組みを教えて下さい。
(蒲原さん)約6年前、当社の前社長がインド駐在経験を持っていたことと、インドのIT企業との協業をきっかけとして、日本クリケット協会のスポンサーを始めました。当初は広告宣伝が主目的でしたが、2022年に私がこのプロジェクトを引き継いだ際、単なるスポンサーシップにとどまらず、クリケットを軸とした多面的な関係構築を目指しました。現在では、日本クリケット協会の本拠地がある栃木県佐野市をはじめとした企業や大学との新たな関係を築き、クリケットを通じた社内コミュニケーション活動も積極的に行うなど、活動の幅を広げています。
役割の柔軟性が創造力を生む!リーダーとフォロワーが入れ替わることで広がる思考の幅
ー ワークショップに参加したメンバーについて教えてください。
(蒲原さん)今回はトライアルとして、社内の23本部のうち興味を示したコーポレート、営業、技術の3本部から、ゆるスポーツに興味を持ちそうな20~30代の社員を中心に選抜しました。合計14名が2チームに分かれて参加しました。
ー ワークショップで期待していたことはありますか?
(蒲原さん)成果を見込んで実施したわけではなく、何が出てくるかをまず見てみようと思いました。社員がこの研修を受けて何を感じ取るかが最も重要だと考えていたからです。また、このような研修が当社にフィットするのかも確かめたかったので、その点を確認するためにも実施しました。


ー 実際にワークショップを実施した感想を教えてください。
(蒲原さん)予想以上に真剣に取り組んでいて感心しました。会社の評価に関係ない中でも、挫折せずに高いモチベーションで最後までやり遂げた点は、非常に良かったと思います。私は、仕事において「考えてから行動する」のではなく、「行動しながら考える」ことが重要だと考えています。前者は考えがまとまるまで動けませんが、後者は実際に動きながら試行錯誤することで常に前進できるからです。システム開発手法に置き換えると、ウォーターフォール(計画後に実行する)とアジャイル(動きながら柔軟に進む)に区別されます。参加者のアンケートからも、この研修にアジャイル的な考え方を感じてくれたように思います。
(大鹽さん)話し合いを重ねても結論が出ず、正解がない中で答えを出すのはとても大変でした。ルールを決める際には「これは少し違うのでは?」と感じることがあっても、それをうまく言葉にできず苦労しました。それでも、自分の抱く「違和感」を一生懸命メンバーに伝え、メンバーも真摯に耳を傾けて理解しようとしてくれました。普段の業務では、うまく言葉にできない違和感を伝えることはないため、とても良い経験になりました。

(蒲原さん)実際にやってみて気づいたのは、創造的な発想が出にくい理由が、メンバー間の知識差にあるのではないかということです。普段の業務では、知識のある人がリーダーとなり、フォロワーができることが多く、その結果、フォロワーがうまく関われなかったり、リーダーの枠から外れた発想が生まれにくくなったりします。しかし今回のワークショップでは、リーダーとフォロワーの役割が柔軟に入れ替わり、役割が固定されないことで思考の幅が広がっていると感じました。
(大鹽さん)フラットに意見を言いやすかったです。
(蒲原さん)その分、物事をまとめるのが難しく、苦労もあったはずですが、それが良い経験になったのではと思います。クリケットのような「全員が初心者の可能性が高いスポーツ」を題材にすることで、ヒエラルキーを排除し、誰もがリーダーにもフォロワーにもなれる環境が作れる点も非常に興味深いと感じています。

「小論文のような思考力を育む」正解なき課題に挑むプロセスが仕事の本質
ー このワークショップで最も印象的だったことは何でしたか?
(蒲原さん)特に印象的だったのは、答えのない課題に取り組む際の戸惑いと、その乗り越え方です。30代くらいまでは、明確なゴールや答えのある中で仕事をすることが多く、答えのない中で探索して進めていく経験が多くありません。しかし、仕事は答えのある「数学の問題」ではなく、答えのない「小論文」だと思っています。仕事が数学の問題なら簡単です。このワークショップでは「正解がない状況でどう考えるか」が問われる内容でした。最初は戸惑う場面もありましたが、次第に試行錯誤を繰り返しながら進めるようになり、このプロセス自体がまさに仕事の本質であり、「小論文」のような思考力が求められる場面だったと思います。
ー 今回のワークショップを踏まえて、今後の展開について考えていることはありますか?
(蒲原さん)今回のワークショップでは、スポーツ創造を通じて新たな学びが得られることが分かりました。若手社員向けの創造力・発想力研修や、管理職向けのリーダーシップ・組織開発研修として活用できる可能性を感じたので、今後は研修としての位置付けを明確にし、より効果的な形で実施したいと考えています。